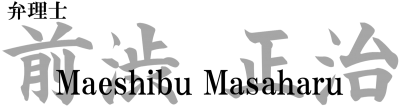※アイキャッチ画像引用:SFCスーパーマリオカート 任天堂 1992
本件、キャラクターの知財保護として画期的な判決であるとともに、自分が請けない類のクソ商標出願についても冷や水を浴びせるものになっており、非常に学ぶべきところの多い判決です。
かつて、「どこでもドアは著作物?」という文章を書きました。
そこで触れている研究成果については、「コンテンツ内オブジェクトによるビジネスについての法的諸問題」というタイトルの論文として弁理士会から出しました。
研究自体は2015年、論文は2016年、実に10年前の話です。
その後、待ち侘びた裁判が起こりました。
ご存知、マリカー事件です。
地裁判決が2018年、高裁の中間判決が2019年、最終判決が2020年です。
すでに5年が経過してしまっていますが、まぁコロナとかあって、個人的にも激動の5年間だったのでゴニョゴニョ、、、
というわけで満を持して解説していきたいと思います。
1.事件の経緯
2.主な争点
3.「マリカー」等の表示を行う行為について
4.被告の商標権について
5.コスチュームを着た人物の写真をサイトに掲載する行為について
6.カート利用者にコスチュームをレンタルする行為について
7.マリオ人形への店舗への設置について
8.店舗の従業員にコスチュームを着用させる行為
9.ドメイン使用について
10.総括
11.今後の論点
1.事件の経緯
説明するまでも無いかとは思いますが一応事件の概要を。
本件は「マリカー事件」と呼ばれる通り、マリオカートに関する裁判です。
秋葉原をはじめとして日本各地でマリオやクッパの格好をした人が乗るミニカートが公道を走っているのを見たことがある方もいるんじゃないでしょうか。
あれ、基本的に外国人の人がやっているんで外国人観光客向けの商売だったみたいですが、任天堂とは無関係な会社がやってたんですね。
自分にとっての唯一無二の推し箱、2019年(と2020年)に閉店した秋葉原の「欧風ギルドレストラン ザ・グランヴァニア」にて、公道を走るマリオコスプレの外国人一団を窓から眺めながら、「あれ、任天堂に許可取らずにやってるんだよね」などと言った推しとの会話が思い返されます。
で、お目溢しの範疇を超えて話題になってきたので任天堂が訴えたという事件です。
おそらく、任天堂のサービスだと勘違いした人が任天堂に問い合わせを入れたり、場合によっては危険だという事でクレームを入れたりということもあったんじゃないかと予想します。
キャラクター知財関係の揉め事あるあるの一つに「問い合わせ」があります。
無許諾でキャラクターを使ったり匂わせたりという行為について、権利者が問題視する要因の一つが「問い合わせ」です。無許諾でのキャラ利用について、権利者側に問い合わせがいってしまうと、権利者側としては「???」なわけです。
で、最悪なケースだとバカなモンスタークレーマーが「ちゃんとライセンス管理しろ!」とかやったりするわけですね。
このマリカー事件が訴訟にまでなった理由は知る由もないですが、あれだけ公道で我が物顔で走られてると、文句言いやすいところに文句を言う輩が出てきてもおかしくない気がします。
2.主な争点
本稿で解説の対象とする争点のみを挙げますと以下の通り。
(1)被告が「マリカー」等の表示を行う行為が不正競争(商品等表示の使用)に該当するか否か▶️
(2)被告の行為が「マリカー」の商標権を有することにより正当化されるか▶️
(3)被告がマリオ、クッパ、ルイージ、ヨッシーなどのキャラクターのコスチュームを着た人物の写真や動画をウェブサイトに掲載するなどして利用することが不正競争(商品等表示の使用)に該当するか否か▶️
(4)被告がマリオ、クッパ、ルイージ、ヨッシーなどのキャラクターのコスチュームをカート利用者に貸与する行為が不正競争(商品等表示の使用)に該当するか否か▶️
(5)被告がマリオ人形を店舗に設置する行為が不正競争(商品等表示の使用)に該当するか否か▶️
(6)被告がマリオ、クッパ、ルイージ、ヨッシーなどのキャラクターのコスチュームを従業員に着用させる行為が不正競争(商品等表示の使用)に該当するか否か▶️
(7)被告が「maricar.・・・」「fuji-maricar.・・・」等のドメインを使用する行為が不正競争(ドメイン不正使用)に該当するか否か▶️
多いな…
これらの判決は全て知財高裁の中間判決で示されています。
というわけで解説していきます。
なお、以下の解説は全て知財高裁判決に基づいています。
また、「キャラクターの知財保護」という観点においては、上の一覧にある(3)からが本番です。
3.「マリカー」等の表示を行う行為について
まず、被告が使用していた「マリカー」関連の表記としては以下の通り。
被告表彰1
1 マリカー
2 MariCar
3 MARICAR
4 maricar
とにかく「マリカー」ですね。
そして、対象となる不正競争防止法の条文は以下の通り、
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
要約すると、他人の有名な表記を使用して商売しちゃダメですよ、という事なんですが、ポイントとなるのは「商品等表示」として有名であるということ。単に有名なだけでは適用されないのがポイントです。この点がキャラクターの知財保護の観点で難しかったポイントです。
(i)任天堂の「マリオカート」「MARIO KART」「マリカー」の知名度について
なので、大前提として任天堂側が「需要者の間に広く認識されているもの」「著名な商品等表示」という条件を満たしている必要があります。
それについての判断は以下の通り。
①「マリオカート」シリーズのソフトの国内累計出荷本数が約●●●●●本で,歴代の国内出荷本数ランキングにも同シリーズから複数の作品がランクインし,人気ゲームとして雑誌に複数回取り上げられていること,
②「マリオカート」シリーズに関してテレビコマーシャルが相当数放送されていること,
③「マリオカート」シリーズに関して,複数のライセンス商品が販売されたり,販売促進活動等に使われたりしている上,それらの中にはゲームとの関連性が薄い自動車販売や道路に関するものが含まれていること
からすると,本件商標が出願された平成27年5月13日の時点で,日本国内において,原告文字表示マリオカートは,マリオ等のキャラクターが登場する一審原告の人気カートレーシングゲームシリーズを表すものとして,「著名な商品等表示」(不競法2条1項2号)になり,これが現在でも継続していると認められる。
というわけで、「マリオカート」という表記については、「人気カートレーシングゲームシリーズを表すものとして」著名であって条件を満たすと判断されました。当然ですね。
また、「MARIO KART」表記についても同様に判断され、それは日本国外の需要者に対しても著名であることが判断されています。
また、「マリカー」という表記が任天堂の商品等表示として周知性(著名性よりも弱い知名度)を満たすか否かについても判断されています。
上に引用した不正競争防止法の条文のうち、「著名」によって判断されるのは二つ目の「二」の条文、対して「周知」というのは一つ目の「一」の条文の「需要者の間に広く認識されているもの」を示す言葉で、「著名」よりもハードルが低い要件です。
何が違うかというと、「他人の商品又は営業と混同を生じさせる」ことが要件として課せられるかが異なります。
「著名」であれば、「他人の商品又は営業と混同を生じさせる」行為じゃなかったとしても使った時点でアウトになるのに対して、「周知」の場合には使っただけではアウトにならず、「他人の商品又は営業と混同を生じさせる」行為として認定されて初めてアウトになります。
原告文字表示マリカーは,一審原告自身が「マリオカート」シリーズを表すものとして用いていたものではないものの,
①ゲームソフト「マリオカート」の略称として,遅くとも平成8年頃には,ゲーム雑誌において使用されるようになっており,
②平成22年頃には,ゲームとは関係性の薄い漫画作品においても何らの注釈を付することなく使用されることがあった。また,
③一審被告会社が設立される前日である平成27年6月3日には,その1日をとってみても,「マリオカート」を「マリカー」との略称で表現するツイートが600以上投稿されたこと
が認められる。
そして,一審被告会社の設立後においても,テレビ番組において,タレントが,一審原告のゲームシリーズである「マリオカート」の略称として「マリカー」を使用していたと発言し,本件訴訟提起に係る報道が出された後には,複数の一般人から,一審被告会社の社名である「マリカー」が一審原告のゲームシリーズ「マリオカート」を意味するにもかかわらず,一審被告会社が一審原告から許可を得ていなかったことに驚く内容の投稿がされた事実が認められる。
以上の事実からすると,原告文字表示マリカーは,一審原告のカートレーシングゲームシリーズである「マリオカート」を示すものとして,遅くとも平成22年頃には,日本国内のゲームに関心を有する需要者,すなわち日本国内の本件需要者の間で,広く知られていたと認められる。
ということで、「マリカー」という表記については、任天堂の商品等表示として少なくとも周知性は獲得していることが判断されました。
(ii)「マリカー」と「マリオカート」との類似について
で、被告の使用は「マリカー」ですので、今回は「マリカー」が任天堂の商品等表示として周知であること、即ち、「他人の商品又は営業と混同を生じさせる」行為も要件として課される条文の適用で判断されたのか?というとそうではありません。
「マリカー」が任天堂の商品等表示として周知であると判断された理由はそこではなく、「マリオカート」の略称として周知であるということをもって被告の使用する「マリカー」が任天堂の著名商品等表示である「マリオカート」と類似するという判断を導いています。
なるほどなぁ。
※被告標章「マリカー」と任天堂の著名商品等表示「マリオカート」の観念類似の判断
原告文字表示マリオカートからは,「マリオのカート」という観念のほか,前記(2)で検討したとおり,一審原告の人気カートレーシングゲームシリーズとの観念が生じる。他方,被告標章第1の1は,上記ゲームシリーズ「マリオカート」を示すものとして周知であるから,日本国内の本件需要者の間では,被告標章第1の1からは,「マリオの車」という観念のほか,一審原告の人気カートレーシングゲームシリーズという原告文字表示マリオカートと同一の観念も生じる。
以上の検討からすると,日本国内の本件需要者との関係で,原告文字表示マリオカートと被告文字表示第1の1(マリカー)は類似している。
「MARIO KART」についても、「車」「カート」「Car」辺りの観念についてのクッションは入りつつも、大枠同様に類似と判断されています。
(iii)不正競争の判断について
そして最終的に不正競争に該当するか否かの判断として以下の通り判断されました。
不競法2条1項2号は,著名表示をフリーライドやダイリューションから保護するために設けられた規定であって,混同のおそれが不要とされているものであるから,一審被告らが主張するような打ち消し表示の存在や本件各コスチュームの使用割合が低いこと(ただし,この点についての一審被告らの主張を採用できないことは,後記6(2)エのとおりである。)といった事情は,何ら不正競争行為の成立を妨げるものではない。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,自ら又は関係団体と共同して被告標章第1を前記第2の2(4),第3の1~3で認定したとおり使用する一審被告会社の行為は,外国語のみで記載されたウェブサイト等で用いることも含めて不正競争行為に該当するものである。
というわけで、「マリカー」「MariCar」等の表記は、任天堂の「マリオカート」が著名であることをもって不正競争との判断です。
特に驚くべき点は無いですが、「マリオカート」と「マリカー」とが類似であるという判断において、客観的な文字構成のみでなく、「マリカー」が「マリオカート」の略称として周知であることを認定した上で観念の類似判断においてそれが参酌されている点が一つのポイントかなと思います。
4.被告の商標権について
被告は「マリカー」という商標権を持っていたので、「その商標権があるから使っていいんだ!」と反論していました。
それについては、
一審被告会社は,周知又は著名な原告文字表示及び「MARIO KART」表示が持つ顧客吸引力を不当に利用しようとする意図をもって本件商標に関する権利をゼント社より取得したものと推認することができる。
したがって,一審被告会社が,一審原告に対し,本件商標に係る権利を有すると主張することは権利の濫用として許されないというべきであり,一審被告らの上記主張は理由がない。
ということで権利の濫用として一蹴されています。
この判断については、
②平成28年11月15日当時に品川第1号店において配布されていた本件チラシには,「マリオのコスプレをして乗ればリアルマリオカート状態!!」と記載されていたこと(甲3,4),
③平成28年8月12日当時に品川第1号店サイト1には,「みんなでコスプレして走れば,リアルマリカーで楽しさ倍増」と記載されるとともに,「マリオ」のコスチュームを着用した人物の写真が同記載に併せて掲載され,また,平成29年2月23日当時に品川第1号店サイト1に「みんなでコスプレして走れば,リアルマリカーで楽しさ倍増」と記載されていたこと(甲6の1,甲35),
④平成29年2月23日当時に,河口湖店サイトに「スーパーマリオのコスプレをして乗れば,まさにリアルマリオカート状態!!」と記載されていたこと(甲6の2)
といった認定により、「顧客吸引力を不当に利用しようとする意図」が裏付けられている形です。
つまり、被告側は任天堂のマリオカートに寄せる意図なく「マリカー」商標を取得して公道カート事業を営んでいたのではなく、寄せる気満々だった点を指摘され、登録商標の使用だという主張が「権利の濫用」であると断罪されているわけです。
他者の生み出した価値に勝手に乗っかってアコギな商売をする上で商標制度を曲解して悪用し、自己の行為を正当化しようとするなど笑止千万!
ということです。
前の投稿でも書きましたが、この商標登録出願の代理を依頼されたとしても自分は絶対に請けません。
「マリカー」というサービス名だけで、マリオカートに全く関係ない、匂わせることも全くないサービスであれば検討の余地はありますが、このサービス内容で「マリカー」なんていう商標登録を行うことが許されて良い道理は存在しません。
登録査定をした特許庁が悪いのかというと即座にそう判断できるものでもありません。
特許庁の審査官は出願された書類のみを見て審査をします。
出願書類には、この出願人がどのようなサービスを行なっているかなんて当然書いてないですから、「マリオカートに寄せて”マリカー”を登録しようとしているからダメ」なんていう審査はあり得ないことです。
そして、日本の制度は性善説に基づいて運営されているわけですから、この被告のように商標権を悪用してマリオカートに寄せて「マリカー」で商売してやろうなんていう前提は商標の審査には持ち込まれません。
「マリカー」という商標と、指定されている商品や役務に基づき、出願人は商標制度の趣旨に則って商標を正当に活用しようとしているという前提のもと、淡々と審査するのみです。
しかし、出願を代理する代理人は違います、依頼者がどんな事業を展開しようとしているのか、それを知らなければ指定商品や役務を検討できませんから、依頼者のサービス内容をしっかりと把握しているはず。依頼者が商標制度を悪用しようとしていることは把握しているはずです。
つまり、性善説を逆手にとって商標登録を行い、その権利を濫用する手伝いをしたのがこの出願の代理人です。
結局、裁判でも権利の濫用と一蹴されているわけで、この商標登録出願は代理した弁理士が金儲けしただけで世の中的には害悪でしかなかったわけです。掛け値なしの悪。
更に、この商標権は様々に分割登録されてばら撒かれた形になっています(全部消滅してるけど)。
こないに手続きやりしくさって、セン(↓)セエ(↓)ぎょうさん儲かりましたなぁ〜。
この代理人はマジで懲戒処分でいい。
5.コスチュームを着た人物の写真をサイトに掲載する行為について
ここまでは「マリカー」という文字表記についての判断でした。
ここからが「キャラクターの知財保護」としての本番です。
今度は「マリカー」といった表記ではなく、マリオなどのコスチュームを着た人物の写真が商品等表示として認められるかという判断です。
写真の内容は以下の通り。
本件写真2には,公道カートに乗車した人物が2名表示されているところ,手前の人物は,少なくとも,原告表現物マリオの特徴(C)ないし(E)を備えているコスチューム(以下,同様の特徴を備えたコスチュームを「本件マリオコスチューム」という。)を着用している。本件写真3には,公道カートに乗車した人物が2名表示されているところ,手前の人物は,原告表現物ヨッシーの特徴(A)及び(B)を備えているコスチューム(以下,同様の特徴を備えたコスチュームを「本件ヨッシーコスチューム」という。)を着用している。
この訴訟の注目ポイントの一つ、
「キャラのコスチュームが商品等表示として認められるか否か」
の判断ですが、結論から先に言いますと認められました。
非常に画期的なことです。
つまり、
著名と言える程の知名度を獲得したキャラのコスチュームは、分野問わず商品等表示として保護され得る。
という判断が下されたということです。
では、判断を順番に見ていきます。
(i)キャラクターの知名度について
まずは、マリオをはじめとしたキャラクターが有名であることが条件ですので、その点が判断されます。
原告表現物マリオは,その人物のイラストとしての基本的な表現上の特徴を同じくする「マリオ」が登場する一審原告のゲームソフト作品の長年にわたる販売及び人気並びにそれに伴う宣伝等により,一審原告の商品の出所を表示する商品等表示となり,遅くとも,国内出荷本数ランキングで2位を,国内及び世界における出荷本数ランキングで5位を獲得した「Newスーパーマリオブラザーズ」が発売された平成18年5月には,日本国内で,一審原告の商品等表示として著名となっており,それが現在でも継続していると認められる。また,遅くとも,「マリオ」が「ギネス世界記録」が発表した「ゲーム史上最も有名なゲームキャラクターTop50」において1位を獲得した平成23年2月頃には,日本国外のゲームに関心を有する需要者の間でも著名となっており,それが現在でも継続しているものと認められる。
このような感じで、ゲームの出荷本数や、ギネス記録の認定を根拠として、商品等表示として著名であることが認められています。
この結論については全く異論はないのですが、出荷本数に基づく著名性の判断については他の例にも広く適用できるかというと疑問は残ります。
マリオのゲームソフトよりも出荷本数は多いけどマリオよりも知名度の低いキャラというのは存在するんじゃないでしょうか。
また、ここで重要なのは単に「有名だ」と認められたということではなく、「商品等表示として著名」と認められていることです。
これは非常に画期的なことで、キャラクターの知財保護の大転換点となり得る判断だと思います。
過去、「キャラクターは著作物ではない、という言葉を都合よく解釈するな。~同人誌違法アップロード事件~の巻」などで、キャラクターの外観、デザインに関する知財保護に関してあれやこれやと書いてきました。
キャラクターの外観、デザインというと、真っ先に想起されるのは著作権ですが、絵、写真、動画などの視覚的な表現物において、著作権法によって保護されるのはあくまでも「作品」を中心とした範囲であって、キャラクターの保護の場合にはあくまでもそのキャラクターが描かれた画稿などを中心した範囲ですので、キャラクターとして同一だから著作権の保護範囲である、という判断が必ず得られるとは限りません。
つまり著作権で保護される範囲とキャラクターとして同一と見做せる範囲というのは必ずしも一致しないという点が難しいところでした。
これに対して、本訴訟においてはキャラクターの知財保護として著作権ではなく不正競争防止法が認定されたということで、今後有名キャラクターの知財保護の基本戦略になり得る重要判決と言えるでしょう。
なお、ルイージ、ヨッシー、クッパについても同様に認められました。
(ii)被告の反論
これに対して被告は
①キャラクターが商品等表示足り得るためには,特別顕著性及び周知性が必要とされるところ,原告表現物マリオで顕著な特徴があるのは「顔」の部分のみである,
②原告表現物については時代やゲームによって造形が異なっている証拠が多数提出されているから原告表現物全体が周知著名とは認められない
という反論をしています。
これはまんざら無理筋な反論でもなく、キャラクターを知的財産として保護する上でのハードルとして従来から議論されていた論理です。
これに対して、①については、
キャラクターが商品等表示足り得るためには,その性質上,特別顕著性は必ずしも必要ないというべきであって,一審被告らの主張はその前提を欠く。
また,(2)アで後述するような特徴を備えた原告表現物マリオは,「顔」以外にも赤い帽子と長袖シャツ,帽子に描かれた「M」のマーク,青のオーバーオール,白い手袋,茶色の靴といったものが複数組み合わされることによっても特徴付けられていて,「顔」も含めた全体に特徴があるものといえ,一審被告らが主張するように,「顔」以外の部分がありふれたもので何ら特徴的ではないということはできず,一審被告らの主張はこの点でも採用することができない。
と判断されています。
これはマリオに限った話ではなく、コスチュームだけなら世間一般にありふれていそうだけれども、有名になった結果として「あのキャラクターの服だ」と想起されるものに対して広く適用される判例になるべきなのですが、もう一つ明確な言葉が欲しかったな、というところです。
例えば、帽子に「M」のマークが無かったら著名とは認められないのでしょうか?
白い手袋がなく、青のオーバーオールと赤いシャツだけならセーフだったのでしょうか?
判決文において「・・・が無かったら認められないけど」みたいな説明がされることはまずあり得ませんが、「・・・といったものが複数組み合わされることによって」にとどまらない、「・・・があるからこそ」みたいな説明が欲しかったところです。
続いて②の反論については、
原告表現物について,時代やゲームによって造形が異なるものがあるとしても,前記ア認定のとおり,原告表現物の特徴と同一かほぼ同一の特徴を備えた「マリオ」,「ルイージ」,「ヨッシー」,「クッパ」が,長年にわたって繰り返し一審原告のゲーム作品等に用いられてきたことからすると,原告表現物は著名となり,それが現在まで継続していると認められる。
と判断されています。
ゲームのナンバリングによってデザインが変わることはあり得ることですが、共通した特徴を持たせておく事がキャラクターの知名度獲得につながるのもまた事実。
ここで言われている「ほぼ同一の特徴」という条件についてもより解像度が上がっていくと、キャラクター保護についての要件が定まっていくかと思います。
この判断こそが今後のキャラクターの知財保護において超重要ポイントになると自分は考えているところで、後段の「キャラクターの類似の範囲」に関わるものです。
できればもっとたくさんの文章で詳細に判示して欲しかったというのが本音です。
(iii)被告写真の内容と任天堂キャラの類似性
上で引用した条文の通り、商品等表示について不正競争行為が認められるためには、使用した表示が「同一または類似」である必要があります。
その点についてどう判断されたのか。
本件写真2及び3中の本件マリオコスチュームと本件ヨッシーコスチュームを着用した各人物の表示は,原告表現物マリオ及びヨッシーの特徴のいくつかを上記のとおりそれぞれ備えているものであり,その外観は原告表現物マリオ及びヨッシーと類似している。また,前記4(2)で述べたところからすると,「マリオカート」シリーズは,「マリオ」や「ヨッシー」等によるカートレーシングゲームとして日本国内外で著名であるということができるから,公道カートに乗り,本件マリオコスチュームや本件ヨッシーコスチュームを着用した各人物の表示を見た本件需要者は,そこから原告表現物マリオ及びヨッシーを想起するものといえる。
したがって,原告表現物マリオと本件マリオコスチューム及び本件ヨッシーコスチューム並びにそれらを着用した人物の表示はそれぞれ類似しているといえる。
すごい判断です。
何が凄いか、
原告表現物マリオ及びヨッシーを想起するものといえる・・・したがって・・・類似しているといえる
ここです。
想起するから(商品等表示として)類似しているという判断になっています。
これは著作権法においては絶対にあり得ないことです。
著作権法はあくまでも「表現」を保護する法律ですから、類似性の判断においてはあくまでも「表現」として類似していることが求められます。
翻案権における「本質的特徴」を具備するかの判断においてはそこから少し広がることもあり得るとは思いますが、それでも「想起する」だけでは絶対に認定されたりしません。
対して、不正競争防止法における商品等表示の判断においては「想起する」ことで類似性が認められるわけです。
これは別におかしいことではありません。
なぜなら、本事件の判決文でも述べられ、先に引用した通り、
不競法2条1項2号は,著名表示をフリーライドやダイリューションから保護するために設けられた規定
だからです。
他人の著名な商品等表示を想起させて無関係な自分の商売をしてはいけないわけです。
いや〜、素晴らしい。
しつこいですが、不正競争防止法2条1項2号によってキャラクターが保護されるというのは、間違いなく今後のキャラクター知財保護において重要な地位を占めることになるでしょう。
(iv)不正競争行為の認定
というわけで、最終的な不正競争行為の認定です。
本件写真2及び3は,平成29年2月23日までに河口湖店サイトに掲載されたものであり,富士河口湖店が,公道カートのレンタルや本件貸与行為等からなる本件レンタル事業を営んでいることからすると,本件写真2及び3は,単に本件レンタル事業の内容を説明するものではなく,一審被告会社によって自己の商品等表示として用いられたものと認められる。
したがって,本件写真2及び3を河口湖店サイトに掲載することは不競法2条1項2号の不正競争行為に該当するというべきである。
重要な点としては、やはり被告の行為、つまりマリオなどのコスチュームを着た人の写真を使用した行為が「商品等表示としての使用」に該当するのか、という点です。
「単に本件レンタル事業の内容を説明するものではなく」と念押ししてある点が重要ですね。
コスチュームを着てカートに乗るサービスですから、コスチュームに乗ってカートに乗っている写真はサービス内容の説明であって商売の看板、つまり商品等表示ではない、という反論を封じたものです。
なお、写真と同様に動画をYoutubeにアップした行為についても不正競争行為が認定されています。
一審被告会社が,公道カートのレンタルや本件貸与行為からなる本件レンタル事業を営んでいること及び本件各動画の前記内容からすると,本件各動画は,単に本件レンタル事業の内容を説明するものではなく,自己の商品等表示として用いられたものと認められる。
したがって,本件各動画をYouTubeにアップロードすることは,不競法2条1項2号にいう不正競争に該当するというべきである。
6.カート利用者にコスチュームをレンタルする行為について
次に、カート利用者にコスチュームをレンタルする行為について、上記と同様に商品等表示の使用に該当するか否かが争われました。
結論から言えば認められたのですが、これもまた画期的な判決です。
この条文はあくまでも「商品等表示」で、言ってみれば準商標法として意識されるものです。
対して、今回対象となるのは、サービス内でレンタルされるコスチュームのデザインです。
商標的な考え方でいうと、「商標の使用」に該当するのか疑問があります。
ここで商標法の観点で考えてみると、少なくとも2つのステップが必要なことがわかります。
本件を商標法で考えると、コスチュームのレンタルが「商標の使用」に該当しなければいけないわけですが、その「商標の使用」に関する条文を見てみると、
第二条
<略>
3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
<略>
三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
ということで、まずはサービスにおいて客にレンタルされるものに「標章を付する行為」が商標の使用とみなされます。
そして、
<略>
4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
一 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
ここで、レンタルされるものを「標章の形状とすること」が「標章を付する」ことに含まれると規定されています。
わかるでしょうか?
つまり、サービスにおいてレンタルされるコスチュームに標章(ここではマリオたちのキャラクターのコスチュームデザイン)を付することが商標の使用であり、そのコスチュームを標章の形状とすることは標章を付することに含まれます。
結果的に、サービスにおいてレンタルされるコスチュームをマリオたちのキャラクターのコスチュームデザインとすることは、商標の使用になるということです。
なんですが、
この判決が得られる前にこの論理を自信を持って主張できたかというと否でして、商標法ではなく不正競争防止法の商品等表示ではありますが、判決として得られたというのは非常に大きいことです。
具体的な判断としては、すでに上記の判断でマリオたちのデザインの著名性、商品等表示の該当性が判断されているために割とシンプルで、
「スーパーマリオのコスプレをして乗れば,まさにリアルマリオカート状態!!」などと,本件貸与行為を強調し,それを前面に出して本件レンタル事業の宣伝が行われてきた。
また,原判決が本件貸与行為は不正競争行為に該当すると判断した後も,本件各店舗において本件貸与行為が継続されていること及び前記1(1)オ(イ)の通り、原判決後の平成31年2月17日の時点で京都店がルイージやヨッシーのコスチュームを着用した者らの写真をウェブサイトの予約ページで用いていること(甲220)からすると,現時点でも本件貸与行為は,一審被告会社がしている本件レンタル事業を特徴付けるものとして,従来と同じく重要な地位を占めているものと推認することができる。
したがって,一審被告会社は,本件各コスチュームを自己の商品等表示として使用しているものと認められる。
重要な点は、「本件貸与行為は,一審被告会社がしている本件レンタル事業を特徴付けるものとして,従来と同じく重要な地位を占めている」というところでしょうか。
「マリオの格好をしてカートで走る」ということがサービスの特徴であるから、そのコスチュームをレンタルする行為は商品等表示として使用していることになる、ということですね。
なお、被告は以下のような反論をしています。
①本件事実実験の結果やインスタグラムにおける投稿(乙120)からすると,本件各コスチュームは,コスチューム群のごく一部を構成するものにすぎず,商品等表示としては使用されていない,
②不競法2条1項1,2号にいう「使用」には貸与は含まれない,
③本件各コスチュームの割合が低いことや打ち消し表示の存在等により本件では混同のおそれがない
これに対し、①については実験の信頼性が低く、インスタも信頼性が不明ということで却下、③については2条1項2号が混同を要件としていないので却下されています。
注目すべきは②の使用に該当しないという点、具体的に被告は
不競法2条1項1,2号が,「使用」と「譲渡」等を区別していること,同項4号~10号,10条1項が「使用」と「開示」を分けていて,同法2条1項3号も「貸し渡し」を明示していることからすると,不競法2条1項1,2号の「使用」には,商品に関する占有や支配関係が移転する「貸与」は含まれない
と主張しました。
これに対する裁判所の判断は以下の通り。
不競法2条1,2号は「商品等表示」について「使用」の語を,「商品等表示を使用した商品」について「譲渡」等を用いているのであり,一審被告らが指摘するのは,単に対象の相違に由来する表現の差異にすぎず,それが一審被告らの主張するような上記解釈の根拠となるものではない。
不競法2条1項4~10号,10条1項も,本件とは異なる営業秘密に関する規定であり,一審被告らの主張するような解釈の根拠となるものではない。
不競法2条1項3号についても,上記と同様に対象が「商品」であることから「貸し渡し」という文言を用いているものと解され,そこから直ちに「使用」に占有や支配が移転する場合を含まないと解することはできない。
まぁ、平たくいうと「言葉尻を捉えるな」というところです。
いや、だって法律の条文なんだから、特に無体財産権という形のないものを保護するなんて危ういことやってんだから、法律の適用は厳格じゃなきゃいけないじゃん!言葉尻捉えたくなるよ!
と言いたくなりますが、この判決を契機に、不正競争防止法における商品等表示の使用行為の類型がより柔軟になっていくことが予想されます。
7.マリオ人形への店舗への設置について
これも注目です。
アニメ、漫画をテーマにしているバーなどのお店でフィギュアを飾っていることは結構あります。
ガンダムであれば、「HY2M 1/12 ガンダム」というビッグサイズのフィギュアが公式から発売されており、それを設置している店舗も存在するでしょう。
そのような行為が商品等表示の使用行為として不正競争に該当するという点が争われたわけです。
改めて、被告の行為の認定を見てみると、
品川第1号店においては,遅くとも平成28年6月4日頃から平成29年2月24日頃までの間,店舗内の入口付近に,入口側に背を向ける方向で,身長120㎝ほどの本件マリオ人形が設置されていた
というものです。
これが単なる店舗装飾ではなく商品等表示として、つまり店舗の看板として使用されていると認定されるのか否かという点が問題です。
これについてどのように判断されたかというと、
公道カートのレンタルや本件貸与行為を含む本件レンタル事業を行っていた品川第1号店において,本件マリオ人形を,前記第2の2(4)で認定したとおり店舗の入口付近に設置することは,前記イ~エと同様に本件マリオ人形を自己の商品等表示として用いるものということができる。
という判断です。
つまり、店舗の入口付近に設置することや人形が外側を向いていることだけでなく、「公道カートのレンタルや本件貸与行為を含む本件レンタル事業を行っていた」ことにも触れられているのがポイントです。
マリオカートに寄せた商売をやっているという前提の中で、120cmのマリオ人形を玄関に置いたら、それは看板的に認識されるやろ、ということですね。
自分は模型を趣味としていますが、上記のHY2M 1/12 ガンダムを設置している模型制作室やガンプラバーなどは全国に複数あると思います。
本判決によってそのような店舗の行為が即座に不正競争に該当するということはないとは思いますが、「公式から許可を得てやってると思った」と誤解されるような商売の場合には要注意ということですね。
なお、被告はこの点について「販売目的で設置していた」という反論を行なっていますが、
販売目的であったことを認めるに足りる証拠はないし,その使用態様や一審被告会社の提供していた役務(本件レンタル事業)との関連性等からすると,仮に販売目的であったとしても,それと商品等表示としての使用は併存し得るといえる
として一蹴されています。
値札をつけていたりとかしたら証拠の出しようもあったと思いますが、それすらしていなくて苦し紛れに主張した、というところでしょうか。
そして、判決文の後段からすると、仮に値札がついていたとしてもアウトのようですね。
8.店舗の従業員にコスチュームを着用させる行為
さてお次は、店舗従業員がマリオなどのコスチュームを着ていることが不正競争に該当するのか、という点です。
ここまでくると結論はある程度予想できますが、上記と同様に不正競争に該当すると判断されました。
まずは判決文の引用
従業員が着用していたのは被告標章第2のコスチュームであると認められるところ,被告標章第2のコスチュームは,前記アで認定した原告表現物の特徴の一部を備えており,かつ,これらのコスチュームを着用し,カートツアーの先導者として公道カートに乗車することは,本件需要者をしてゲームシリーズ「マリオカート」に登場する「マリオ」,「ルイージ」,「ヨッシー」及び「クッパ」を想起させるといえ,原告表現物と上記各コスチューム及び同コスチュームを着用して先導を行う従業員らの表示はいずれも類似するといえる。
そして,上記のように従業員に被告標章第2のコスチュームを着用させる行為は,自己の商品等表示としてこれを使用するものといえるから,従業員に被告標章第2のコスチュームを着用させて,カートツアーのガイドをさせる行為は不競法2条1項2号の不正競争行為に該当する。
このような判断ですが、「自己の商品等表示としてこれを使用するものといえる」という結論に至る説明がいまいち薄いと感じます。
コスチュームの貸与の際と同様に商標法上の「使用」の概念に照らして考えてみると、
四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
この辺りを基準として、上記と同様に「標章の形状とすること」が「標章を付する」ことに含まれるということで認定、というところでしょうか。
文脈的には「これらのコスチュームを着用し,カートツアーの先導者として公道カートに乗車することは,本件需要者をしてゲームシリーズ「マリオカート」に登場する「マリオ」,「ルイージ」,「ヨッシー」及び「クッパ」を想起させる」というところが一番の理由だとは思いますが、「想起させる」だけで商品等表示、つまり商売上の看板として使っているというのはいかにも乱暴です。
実際には、マリオなどのキャラクターが想起された上で、マリオ人形の設置の際に判示された通り、サービス内容(公道カートのレンタルや本件貸与行為を含む本件レンタル事業)との関連を考慮すると商品等表示に該当し得る、ということかと思います。
9.ドメイン使用について
「maricar.・・・」「fuji-maricar.・・・」等のドメインが使用されていた点についても、不正競争であると判断されました。
不正競争防止法におけるドメイン使用の条文は以下の通り。
十九 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
まず、「maricar.・・・」「fuji-maricar.・・・」などのドメイン表記が任天堂の「MARIO KART」と類似であることについては冒頭の表記における不正競争の判断と同様。
これに加え、ドメイン名の使用における不正競争では「不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的」いわゆる図利加害目的が判断されます。
まぁここまでの判断を踏まえれば当然なのですが、
一審被告会社が,「マリオカート」シリーズに登場する一審原告の著名な商品等表示である原告表現物に類似した本件各コスチュームの貸与行為を現在まで継続していることを考え併せると,前記5と同様に,一審被告会社は,周知又は著名な原告文字表示マリオカート及び同マリカー並びに「MARIO KART」表示の高い顧客吸引力を利用して,不当に利益を上げる目的で,本件各ドメイン名を使用しているものと認められ,不競法2条1項13号にいう「不正の利益を得る目的」を有していたと認めることができる
と判断されています。
被告は主な受容者が外国人だからとか色々反論していますが、取るに足らない感じで一蹴されています。
10.総括
というわけで、かなり多岐に渡る判断が下された、非常に学ぶところの多い判決となりました。
最も参考になる点としては、やはり
マリオ、ルイージ、クッパ、ヨッシーのレベルで有名になったキャラクターは、不正競争防止法の著名商品等表示として保護される
という事です。
繰り返し述べている通り、キャラクターの知財保護というのは、あくまでも表現物を保護することが前提となる著作権法において、難しい場合があります。
明らかに「あのキャラクターだ」という態様であったとしても、それが外観的に表現物として明らかでない態様であれば著作権法の保護対象ではありません。赤がトレードマーク、三倍速い、独立蜂起した軍のエースパイロットにして独立運動の祖の息子が世を偲ぶ姿、という設定、世界観は著作権法では一切保護されません。
また、外観的な要素、キャラクターのデザインに関する部分も、基本的に作品として描かれた画稿の保護を中心とする著作権法においては、同キャラクターで新たに書き起こされた画稿に対する権利範囲には限界が存在します。
そのような不安定なものであったキャラクターの知財保護において本判決が持つ意味、特に
想起させる
という言葉が用いられた意味は非常に大きいものです。
上述した目に見えないキャラ設定や世界観であっても、それを想起させるような外観的な特徴が存在することを前提に、「想起させる」という理由に基づいて不正競争行為として認定される可能性があるのではないでしょうか。
そして、本判決を受けてキャラクターの知財保護という観点で言えることがあるとすれば…
ミッキー保護のためにダラダラと引き伸ばされてる著作権の保護期間だけど、著名化しれてば特に保護期間に限界なく商品等表示として保護されるわけだし、著作権の保護期間短くしない?
やっぱ著作権の保護期間なげぇよ。
11.今後の論点
ただし、本判決で全てがクリアになっているわけではありません。
不正競争防止法の商品等表示としてキャラクターが守られていくとしても、まだまだ論点となる部分は残っています。
(i)「商品等表示として著名」のハードル
今回はマリオをはじめとしたマリオシリーズのキャラを対象として「商品等表示として著名」であることが認められました。
これは、ゲームのキャラクターであったことが非常に大きい要素になっていると予想します。
「ゲーム」という商品の看板として用いられてきたことが非常に大きいく作用しているはずだからです。
なので、同じく任天堂のゼルダの伝説のリンク、カプコンのロックマン、セガのソニック、スクエニのドラクエのスライム、などは、同じ土俵の上で、裁判にて示されたような出荷本数やその他のランキング的な情報に基づいて判断することができるでしょう。
対して、ドラえもんならばどうでしょうか?
ドラえもんは間違いなく有名ですが、「商品等表示として著名」でしょうか?
ゲームや玩具などでも当然に用いられてはいますが、ドラえもんが有名なのは藤子・F・不二雄先生の漫画のキャラクターやそれを原作とするアニメのキャラクターとしてです。
何かの商品の看板として有名になっていると言えるのかについては、本判決では判断されていない新たな論点として争われることになると思います。
漫画やアニメ、すなわちコンテンツの看板であることは、果たして不正競争防止法の商品等表示として認められるのか?
(ii)誰の商品等表示なのか?
今回はマリオということで、間違いなく任天堂の看板と言えるキャラクターが対象でした。
対してドラえもんが商品等表示だったとして、果たして誰の商品等表示なのでしょうか?
藤子・F・不二雄先生でしょうか?小学館でしょうか?テレビ朝日でしょうか?シンエイ動画でしょうか?
藤子・F・不二雄先生が創作したキャラクターであることは間違いないわけですが、不正競争防止法上の商品等表示として認められるためには、あくまでも商品等表示として長らく使用されてきたことにより、その商品の供給者の看板として人々に認知されて「著名」となることが条件です。
藤子・F・不二雄先生が創作したことは、直ちに藤子・F・不二雄先生の商品等表示であることを意味しません。
(iii)キャラクターの同一性の範囲
今回の判決にて、息の長いキャラクターのデザインが時代によって変遷していく場合について一定の判断が示されている点は非常に注目すべき点です。
再度引用しますと、
原告表現物について,時代やゲームによって造形が異なるものがあるとしても,前記ア認定のとおり,原告表現物の特徴と同一かほぼ同一の特徴を備えた「マリオ」,「ルイージ」,「ヨッシー」,「クッパ」が,長年にわたって繰り返し一審原告のゲーム作品等に用いられてきたことからすると,原告表現物は著名となり,それが現在まで継続していると認められる。
と認定された点は、今後のキャラクター保護において非常に大きな意味を持ってくると思います。
そして、「表現物の特徴と同一かほぼ同一の特徴を備えた」という点の判断基準が重要なポイントになってくると予想します。
その判断が、最終的に「商品等表示として類似の範囲である」という判断につながってくることになるわけです。
以上、マリカー事件の解説でした。
キャラクターの知財保護についての新たな可能性が示されるとともに、クソ商標について冷や水を浴びせる判決であることがお分かり頂けたかと思います。
バイブルとするお気に入りの判決はいくつかあるのですが、新たに一つ追加されることとなりました。
そして願わくば、ゲーム以外のキャラクターについて同様の訴訟が起こり、上述したような論点が明らかになっていって欲しい、自らの知見を増やすために他人の争いを望むばかりです。