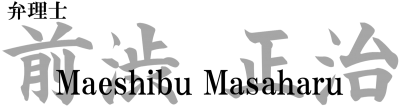趣味で模型をやってまして、展示会なんかにもちょくちょく出品したりしてます。
つい先日は茨木市で開催されたIBA模展に出展してきました。
設置完了。#奈良北模型製作会 卓にて#IBA模展 pic.twitter.com/lPgO0cUsce
— 前渋“CIV”正治@ヲタク弁理士 (@shibuaznable) July 27, 2025
右下の三作品が自分の作品です。
今後の予定としては、
2025/8/16-17 KCF2025 マイドームおおさか 2階C+Dホール
ロボットなし、モデラー生活初のオールフィギュア展示
84番「八龍会」名義
お待たせしました。#KCF2025 の卓配置が完成しましたので公開いたします。
— コジマ塾 (@kozimajyuku) August 3, 2025
画像では文字が読み辛い個所もあると思いますのでPDF版をGoogleドライブで公開しています。
(ダウンロード可)
KCF2025会場配置1https://t.co/uoVHKLOSkH
KCF2025会場配置2https://t.co/hCA70VHRWy
KCF2025参加リスト… pic.twitter.com/DlIPjXYFhy
2025/8/24 柏原市民文化会館リビエールホール 地下レセプションホール
過去に作った仕掛けモノや大物をバージョンアップして展示予定
25番「CIV」名義
HPトラブル中で更新できていませんが夏の展示会の募集開始します。例年と会場に変更があります。大卓1800x600(mm) 1000円、半卓は900x600(mm) 500円を予定しております。出展希望の方は本アカウントDMないしメールにて、サークル名、代表者氏名、代表者連絡先(メール、TEL)をご連絡お願いします。 pic.twitter.com/XF53YCPFN0
— 趣味人会 (@Musyozokusyumi) May 11, 2025
といったところ。
お近くでご興味のある方はぜひお越し下さい。
さておき、今回はそんな展示会についての知財のオハナシです。
展示会には展示物に対してレギュレーション、規則が定められていることが常ですが、その基本的な内容は、
・作ったもの、組み立てたものであること(フィギュアなどの完成品をそのまま展示するのはNG)
・海賊版キット、違法コピーキット、それらを含むものはNG
・フルスクラッチ(粘土などでゼロから自分で作ったもの)は展示可能
・18禁的なものはNG
といったところです。
この上なく妥当なもので、反対する気持ちはサラサラ無いのですが、いやしくも知財の専門家としておマンマ食べてる身としては疑問がわく部分があるわけです。
それは、
・海賊版キット、違法コピーキット、それらを含むものはNG
に対して、
・フルスクラッチ(粘土などでゼロから自分で作ったもの)は展示可能
というところ。
実はこの二つ、
権利者の許諾の外にある
という点において法的に全く同じ状態なんですよね。
なので、法的に厳密に考えると海賊版がダメなのにフルスクラッチがOKな理由が見当たらないんじゃないかな、と思うわけです。
というわけで、今回は模型展示会において海賊版がダメでフルスクラッチがOKな理由を法的に考えていきたいと思います。
目次
1.展示に関する著作権
2.海賊版・違法コピーキットの法的な状態
3.フルスクラッチの法的な状態
4.判例はどうか
5.お目溢し
6.それでもやっぱり法的な根拠が欲しい
※※※※※※※※※※※※
1.展示に関する著作権
まずは模型展示会などで作品を展示する際に関係してくる著作権について確認していきます。
(1)著作権の源泉
模型展示会で展示される作品の著作権を法的に厳密に検討するのであれば、そもそもの著作権の源泉を明らかにしておく必要があります。
そこで、何か一つ具体的なものを想定して話をわかりやすくしておきましょう。
とすれば、やはりこの方しかいないでしょう。
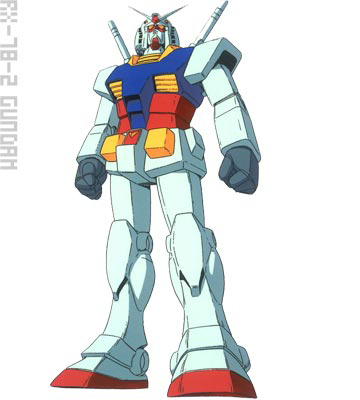
(初代)ガンダムですね。
このガンダムの立体物、プラモデルについての著作権を念頭に色々と考えていきます。
で、「ガンダムの著作権」と一口に言って解決するかというと、全くそんなことはないわけですね。
このガンダムについて、言ってみればこの「デザインの著作権」というものは厳密には存在しません。
著作権の対象となる著作物というのは、あくまでも「表現されたもの」ですので、「デザイン」という抽象的な概念についての権利というのはあり得ないわけです。
ではどのように考えるかというと、今まさに引用させてもらったこのイラストです。
おそ松さん同人誌事件でも判示されている通り、ガンダムのデザインが初めてこの世に誕生し、世の中に提示された画稿が全ての権利の源泉となるわけです。
で、自分は1979年生まれ、ガンダムの放送開始の年に生まれていますので、ガンダムについて初めて世に提示されたイラストがどれなのかというのは確実には知らないのですが、諸条件や漫画「ガンダムを作った男たち」より推測する限りはこのイラストでしょう。
このイラスト(大元イラスト、とします)の著作権をガンダムという機体のデザインに関する全ての著作権の源泉として、複製権や翻案権によって処理されるのが「ガンダムの著作権」です。
で、肝心の模型についてはどうかというと、
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
まずは、翻案権にて規定されているところの「変形」、「その他翻案」という文言に基づき、イラストから立体物への変形と考えたり、その他翻案という概念の中に立体化が含まれるものと考えたりすることで、ガンダムの立体物、プラモデルを作ることは大元イラストの翻案であると考えられます。
なので、勝手にガンダムの立体物を作ることは、大元イラストの翻案権を侵害することになるわけですね。
また、バンダイをはじめとした各種のメーカーがガンダムの立体物を商品としてリリースする際、特に近年の商品については、大元イラストからは大幅にアレンジが加えられたデザインとなっています。
こんな感じで。
そうすると、大元のイラストだけでなく、アレンジを行なったデザイナーさんの創作という部分も入ってくることになるわけです。
ガンダムのアレンジをするデザイナーとして有名なところと言えば、例えばカトキハジメ氏です。Ver.Kaなんて感じでリリースされたりしています。
カトキハジメ氏によってアレンジデザインされたガンダムの立体物については、
大元イラスト(元の著作物)
↓
カトキ氏のアレンジイラスト(二次的著作物)
↓
Ver.Ka立体物(二次的著作物の翻案物)
と、こんな感じになります。
その場合の権利はどうなるかというと、直接的に立体化の元となっているカトキ氏のアレンジイラストの著作権が関係してくることはもちろん、大元イラストの著作権についても、
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
こちらの二次的著作物の条文に基づいて関係してくることとなります。
立体物の著作物を検討する際、立体物そのものが権利の源泉となる著作物であるという場合はかなり少ないのではないでしょうか。
カーモデル、ミリタリーモデルなど、世の中に実際に存在する物の模型であったとしても、そのデザインについては立体物が作られる前にまずデザイナーさんの画稿や設計図が存在するのではないかと思います。
多くのプラモデル、模型の著作権についてはこの通り、その立体物のデザインが初めて確定した画稿の著作権が源泉として考えられ、立体物はその翻案物であるとして権利処理が検討されることとなります。
(2)模型の展示に関わる著作権
まずはいきなり条文です。
(展示権)
第二十五条 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
この通り、著作権法には「展示権」という権利が「公に展示する権利」として規定されています。
が、ここで日本語として読んで厄介なのは「原作品により」という文言ですね。
この「原作品により」という文言ですが、例えば版画のような同一のものが複数制作され、そのすべてが原作品的価値を有するようなものであればすべてが「原作品」として認められるものとされています(中山著作権等)。
そして、模型に関連して非常に参考になるものとして、鋳型により同一のものが複数制作される彫刻なども同様だとされています(同上)。
ですので、大量生産品であるプラモデル等も、そのすべてが「原作品」として認められることについては問題ないようです。
すると、購入したガンダムのプラモデルを組み立て&塗装などして完成させ、模型展示会で展示する行為というのは、そのプラモデルを立体物としてデザインして創作することによって生じた著作権や、その元となっているイラストの著作権のうち、展示権を侵害するというのが原則ということになりそうです。
これに対して、
(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
第四十五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
このような条文があります。
詳しく条件と効果を整理してみますと、
条件は、
・美術の著作物若しくは写真の著作物であること
・その著作物の原作品の所有者(又はその同意を得た者)であること
・その原作品を用いること
効果は、
・その著作物を公に展示することができる
ということになります。
大量生産されたプラモデルの一つ一つが「原作品」として認められるであろうことは上述した通りです。
なので、少なくともメーカーのプラモデルを正式に購入して所有権を取得し、それを制作したモデラーが作品を模型展示会に出展することは許されるということになるでしょう。
※※※※※※※※※※※※
2.海賊版・違法コピーキットの法的な状態
さて、本題のフルスクラッチ&海賊版についてです。
まずは海賊版から。
注目点は、上記の展示が許されるという条文(45条)が、適用されるか否かということになります。
ここで問題なのは、45条では「著作物」としか規定されておらず、海賊版的なものが除外されるという趣旨の規定が存在しないことです。
なので、大元の著作物(ガンダムで言えば上記のガンダムのイラスト)の著作権がクリアされていないものが、45条における「美術の著作物」「原作品」に含まれるのか否かということを、45条の条文やその立法趣旨に基づいて類推するしかありません。
ではまず、45条についての基本書の解説を見てみます(中山著作権)。
・・・美術や写真の原作品を、ロビーやショウウインドウ等に展示することは通常のこととして行われている。美術品・写真の原作品の所有者には公に展示できて当然という意識もあろうし、展示の度に著作権者から許諾を求めるということも現実的ではない。また、原作品の譲渡の際に展示権の処理をする必要があるとすると取引が混乱する原因ともなる。所有者に対しこのような展示を認めないと、原作品の商品価値が低下しかねない。その上、そのような展示は所有権に基づく使用収益とも考えられるので(民206条)、理論的には物の所有権と著作権の交錯の処理を解釈で行うという困難にも直面することになるため、展示権と所有権との調整規定が置かれている。
ここでも、海賊版については明確には語られていません。
が、ここで語られている趣旨から考えれば海賊版が45条の「原作品」に含まれないことは割と明らかなんじゃないかなと思います。
というのも、「展示権と所有権との調整」として解説されている45条の規定は、25条の展示権を打ち消す規定ですから、対象となる25条の展示権に関する著作物の「原作品」である必要があるわけですよね。
海賊版がそうではないことは明らかです。
また、「展示の度に著作権者から許諾を求める」、「原作品の商品価値」など、適法な著作物であることを前提に語られているようにも読めますから、海賊版、違法コピーという形で著作権者の管理の外側で得られた所有権に対して、そのような著作権への対抗力を認める合理性は無いのかなと思います。
※※※※※※※※※※※※
3.フルスクラッチ作品の法的な状態
ではフルスクラッチ作品はどうでしょう。
言うまでもありませんが、法的な状態は海賊版と一緒、打ち消し対象となる展示権(25条)にまつわる著作権についての「原作品」ではありません。
海賊版との間に違いがあるとすれば「自分で作った」という点。
この点を足がかりとして、なんとかセーフという結論を導けないでしょうか。
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
<略>
私的に複製することはOKとされてますが、これはあくまでも「複製」ですので原作品にはなり得ず、45条の適用対象からは外れてしまいます。
更には、
(複製物の目的外使用等)
第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
一 第三十条第一項、・・・に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(略)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示(略)を行つた者
とある通り、フルスクラッチして自分で楽しむだけなら許されていたものが、「公衆への提示」によってむしろ許されなくなってしまうという条文すら存在します。
う〜ん、どうやら条文からセーフという明確な結論を導くことは難しそうです。
※※※※※※※※※※※※
4.判例はどうか?
条文から結論を導けない場合には判例に頼るしかない、ということで判例を検索してみるわけですが、「展示権×原作品」で検索して出てくる判例はなんとたったの11件。これは極端に少ないです。
つまり展示権の侵害において対象となる展示物が原作品に該当するか否かが争われた判例が極端に少ない、なんなら無いことを意味します。
事実、11件全てにざっと目を通しましたが、45条の「原作品」に該当するか否かが争われたものはありませんでした。
だから何も参考にならないか、というとそういうことでもなくて、希望的観測を含みつつで検討すると、判例が少ないということは展示権を問題視する権利者が少ないということを意味する、はずです…多分…
著作者とは無関係に制作された立体物が美術の著作物の原作品に該当するか否か、それにより45条の原作品による展示が認められるか否か、という判断ではありませんでしたが、模型展示会における模型の展示、特に、市販の模型商品を購入し、塗装や形状をアレンジして制作して展示することについて多少参考になりそうな判例があったので紹介しておきます。
※飯村コートです
観音像頭部すげ替え事件(知財高裁平成21年(ネ)第10047号、原審東京地方裁判所平成19年(ワ)第23883号)
<事案の概要>
・原告は仏師一家の一人
・原告の父や兄(いずれも故人)と共同で制作した観音像を被告である寺に納めている
・被告の寺では、原告一家から収められた観音像について、原告とは異なる主体である被告Yに依頼して寺での公衆への閲覧に際して都合がよくなるよう頭部をすげ替え、その状態で展示していた
・原告が、すげ替えた頭部の原状回復、それまでの展示の差し止め、損害賠償、謝罪広告を求めて提訴
・被告による反対主張の一つとして、45条による展示の自由が主張されている
<裁判所の判断(抜粋)>
裁判所で認められた経緯としては、
①被告寺が原告の兄Rに観音像の制作を依頼し、Rが観音像を制作した
②Rが制作した観音像を現場に安置すると、拝観者が見る角度の関係で観音像の表情が異なって見えてしまう(驚いたような表情や睨みつけるような表情)
③そのため、被告寺がRに対して修繕を依頼した
④修繕依頼に対して原告自身が対応しようとしたが無理だった
⑤被告寺は原告一家とは異なる被告Yに相談したところ、修繕ではなく頭部そのものをすげ替えるしかないと回答した
⑥被告寺はYの回答に応じてYにすげ替えを依頼した
⑦被告Yは全くの部外者というわけではなく、長年にわたってRの弟子としてやってきた
⑧観音像の元の頭部は被告寺に保管されており拝観者が閲覧可能な状態にあった
といったところで、このような経緯に基づいて以下の通り判断されています。
被告らによる本件観音像の仏頭部のすげ替え行為は,確かに,著作者が生存していたとすれば,その著作者人格権の侵害となるべき行為であったと認定評価できるが,本来,本件原観音像は,その性質上,被告光源寺が,信仰の対象とする目的で,Rに制作依頼したものであり,また,仏頭部のすげ替え行為は,その本来の目的に即した補修行為の一環であると評価することもできること,交換行為を実施した被告Yは,Rの下で,本件原観音像の制作に終始関与していた者であることなど,本件原観音像を制作した目的,仏頭を交換した動機,交換のための仏頭の制作者の経歴,仏像は信仰の対象となるものであること等を考慮するならば,本件において,原状回復措置を命ずることは,適当ではないというべきである。
というわけで、原状回復措置や、謝罪広告の掲載は否定されています。
また、展示権についても以下の通り判断されています。
Rは,被告光源寺からの,観音像の制作依頼に対し,これを承諾して,本件原観音像を制作したものである。ところで,観音像は,その性質上,信仰の対象として,拝観者をして観覧させるものであり,このような観音像の本来の目的に照らすならば,Rが,自己が制作した観音像の展示については,一般的,包括的かつ永続的に承諾をした上で,制作したとみるのが自然である。したがって,原告が,Rから相続したと主張する展示権に基づいて,公衆の観覧に供することの差止め及びこれに関連する原状回復を求めることが許される余地はないと解するのが合理的である。
本件観音像は,本件原観音像の眼差しを修正する目的から,頭部を交換したものであり,本件原観音像そのものではないが,前記4の事実経緯等に基づき総合判断するならば,原告の有する展示権に基づく,本件観音像の展示差止めの請求が許されないのは同様である。
判決文において明確に「45条の原作品に該当する」と言われているわけではないのが非常に歯痒いところです。
ただ、この判決文によって読み取ることができるのは「著作物の制作の経緯や制作の目的に基づいて展示権が制限され得る」ということです。
これを模型展示会に当てはめてみれば、模型という趣味、市販のプラモデルキットを購入して公式のデザインとは異なる独自のアレンジを施して制作することは当然に行われて然るべきことであって、権利者の有する展示権に基づく展示差止めの請求は許されない、という判断は大いにあり得ることかと思います。
しかし、被告は45条を主張しているのになんで「頭部がすげ替えられていても原作品に該当する。45条により展示は許される」という判断をしてくれなかったんだ…
※※※※※※※※※※※※
5.お目溢し
というわけでフルスクラッチ作品や海賊版キットの展示の話に戻りますと、
判例が少ないということは展示権を問題視する権利者が少ないということを意味する、はず
という希望的観測に対応する法的な状態、すなわちお目溢しです。
第百二十三条 第百十九条第一項から第三項まで、第百二十条の二第三号から第六号まで、第百二十一条の二及び前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、次に掲げる行為の対価として財産上の利益を受ける目的又は有償著作物等の提供若しくは提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的で、次の各号のいずれかに掲げる行為を行うことにより犯した第百十九条第一項の罪については、適用しない。
<略>
いわゆる「親告罪/非親告罪」というやつです。
「親告罪:権利者が問題視しないのであれば警察も手出しできない」という、つまり「権利者のお目溢し」です。
「非親告罪/権利者が問題視していなくても警察が立件できる」ということで、悪質性が高い、社会に対する影響が大きいと考えられます。
海賊版、違法コピーという形で権利者の目を盗んで利益を得たモノ vs 個人が自分の手で制作した一品モノ
どちらが権利者にとって問題視すべきか/問題視する必要がないか、これは明らかですよね。
自分で独自に立体物を制作してそれを非営利、入場無料の模型展示会に出展したとしても、権利者が被る損害はゼロに等しいですし、なんならその評判に基づいて商品化の判断を行うこともできるかもしれない、権利者にはメリットの方が大きいと思います。
他方、海賊版の展示となるとそうはいきません。
海賊版というのは権利者が本来得られるはずのライセンス料をすり抜けている状態ですから、権利者には間接的に損害が発生していますし、権利者が正規品として立体物を発売していればその売り上げにも影響します。
また、「海賊版を見逃している」という状態は次の海賊版を誘発する、その状態そのものが権利者にとってはリスク、看過できない状態ですから、お目溢しする必然性は基本的にはないモノです。
ごく稀に、無許諾でも盛り上がってくれれば作品としてはプラス、みたいな場合もあるかもしれませんが、基本的にはあり得ません。
特に、上記条文の”2”に記載の通り、「財産上の利益を受ける目的又は有償著作物等の提供若しくは提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的」であれば非親告罪となる場合があることが規定されています(ただし、展示については規定されていない)。
この規定は「有償著作物について・・・」という規定になっていて、ゼロから立体化して制作された海賊版が適用対象となるかは不明確ですが、正規で流通した立体物の違法コピー品の売買については確実に非親告罪となり、権利者が問題視しなくても警察が立件できることが規定されています。
とすると、展示権が直接的に規定されていないとしても、非親告罪となる違法コピー品を展示会から排除するというのはこの上なく妥当な判断ということになります。
お目溢しの可能性として海賊版とフルスクラッチ作品とでは雲泥の差があるのは間違いありません。
※※※※※※※※※※※※
6.それでもやっぱり法的な根拠が欲しい
とはいえ、権利者のお目溢しに頼るというのはどうにも座り心地が悪い。
なんとかして法的な根拠を見出せないモノでしょうか。
そこで、展示権(25条)に対して直接的に言及されていなくても、他の支分権の観点から類推することはできないか考えてみます。
(1)私的複製の拡大解釈
やはり最初に頭に浮かぶのは上述した私的複製(30条)です。
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
<略>
この条文において対象となっているのは「複製」なので、公での展示は対象にはなっていないのですが、仮に展示が対象だったとして、次に問題になるのは「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」というところ。
展示会にも様々な規模がありますが、少なくとも数十人以上が一堂に介して展示物を持ち寄って展示を行うので、やはり現状の30条から類推してフルスクラッチ作品を模型展示会で展示することが許されるというのは難しいです。
が、この趣旨は権利者の利益を損なわない範囲で著作物の利用を推進し、法目的である文化の発展に寄与しようというモノですから、一定の条件のもとでフルスクラッチ作品の展示が許されるような判断がこの延長線上にあっても良いんじゃないかと思います。
「一定の条件」としては、
・観覧者から入場料を徴収していないこと
・展示会の開催によって出展者が利益を得ていないこと
といったところでしょう。
(2)営利を目的としない上演等の拡大解釈
こんな条文もあります。
(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
これは、たとえば学校における演劇などに適用される条文で、営利目的が一切ない場合には、公表された著作物を利用できるというモノです。
が、その対象は上演、演奏、上映、口述となっていまして、展示は対象になっていません。
が、これも上記と同様、立法の趣旨に鑑みれば展示に適用される判断があっても良いと思います。
特に、高校や大学の文化祭などにおいて、部活動の成果展示が行われることは普通にありますし、昨今では模型部というのがあって、プラモデル作品はもちろん、部員が協力して制作した大物のフルスクラッチ作品が展示されているということも珍しくありません。
実際、自分も知り合いの大学学園祭を訪れ、模型サークルの展示会を見に行ったことがありますが、大物のフルスクラッチ作品が展示されていました。
この場合にも上記と同様、
・観覧者から入場料を徴収していないこと
・展示会の開催によって出展者が利益を得ていないこと
といったところが条件になってくるかと思います。
というわけで、模型展示会におけるフルスクラッチ作品/海賊版・違法コピー品の展示に関する法的な検討でした。
条文や判例に基づく明確な「自分で作ったフルスクラッチ作品ならセーフ」という結論はないものの、他の支分権も含めて立法趣旨から類推するならば商業的性質のない展示会であればセーフという結論には無理はないのかなと思う次第。
逆に、商業的な性質が濃い展示会においては、少なくとも権利者のお目溢し以外でセーフを主張できる根拠は薄くなっていくのではないかと思います。
まぁ、自分にはフルスクラッチにより作品を制作するようなスキルも気力もないので関係ないことなんですけどね。
それより、今週末の展示会の作品まだ完成してない…